
J-SOXは、財務報告の信頼性を確保することを目的とした日本の法制度であり、国内の拠点だけでなく、海外子会社にも内部統制の整備と運用が求められます。また、2024年4月の内部統制実施基準の改訂により、海外子会社の重要性が言及されています。しかし、実情は、海外子会社で内部統制報告制度の目的や内容が十分に理解されず、「本社主導で一方的に押し付けられるもの」として受け取られてしまうことも少なくありません。その結果、J-SOX対応が海外子会社にとって負担に感じられ、十分な協力が得られていないことも多く見受けられます。こうした状況を回避するには、内部統制報告制度の「背景」や「意義」を現地の言語や文化に配慮して丁寧に説明し、本社と海外子会社でJ-SOXに対する認識を共有することが重要です。
今回の記事では、成功事例・失敗事例を紹介しながら、海外子会社のJ-SOX対応における留意点を解説します。
海外子会社がJ-SOXに非協力的になる原因
J-SOXは、金融商品取引法にて、上場企業に対し、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・評価・報告を義務付けている制度です。連結財務諸表に影響を与える子会社は、国内外を問わず制度対応の対象となります。しかし、海外子会社において、J-SOXに対し、非協力的な態度が見られるケースが少なくありません。その主な原因として、以下の点が挙げられます。
第一に、海外子会社における制度そのものに対する理解不足が挙げられます。J-SOXは日本の法令に基づく義務であり、親会社にとっては避けられない対応事項です。しかし、海外子会社に対し、その重要性が十分に説明されていないことが多くあります。そのため、J-SOXを「本社独自のルール」や「日本だけの制度」と誤解し、自分たちには関係が薄いと認識されることがあります。
第二に、現地の実情(文化や業務慣習の違い)を考慮しない一方的な本社からの対応が挙げられます。本社が日本でのやり方をそのまま海外子会社に適用し、現地の業務実態やリソース状況が考慮されない非現実的な対応を海外子会社に求める結果となっていることがあります。このような進め方では、現地の理解や納得を得られず、結果として非協力的な態度や反発を招く要因となります。
海外では人材の入れ替わりが多い傾向があり、J-SOXに関する知識や運用ノウハウの継承が難しいという構造的な課題もあります。新しい担当者への教育や情報共有が不十分だと、非協力的な姿勢が継続してしまうこともあります。

J‐SOX評価前に現場に“重要性”を伝えること
海外子会社におけるJ-SOX対応を進める上で、第一に重要なのは、J-SOXに関する共通理解を築き、J-SOXをしっかりと浸透させることです。そのためには、「J-SOXが日本の上場企業にとって法的な義務があること」や、「グループ全体の信頼性に関わる取り組みであること」を明確に伝える必要があります。また、本社が一方的に進めるのではなく、現地と「協力して進める取り組み」であるという姿勢を示すことで、現場との距離を縮めることができます。J-SOX対応を始める前に、簡潔かつ実務的な説明資料を準備することも有効です。さらに、打合せを通じて、現地からの意見を取り入れ、「本社から押し付けられた仕事」という印象を和らげ、前向きな対応を引き出すべきです。
次に大切なのが、現地の状況に配慮することです。業務が忙しい海外子会社にとって、J-SOXは「担当業務とは別の負担」と感じられることがあります。そのため、現地の状況を理解し、無理のないスケジュールを提案することが大切です。特に、国や地域によっては、繁忙期や休日の考え方が異なるため、柔軟にスケジュールを調整することが信頼関係の構築につながります。本社の都合だけで日程を決めるのではなく、現地の状況や担当者の予定を尊重する姿勢が求められます。その際、メールや文書で一方的に依頼するのではなく、背景や目的を丁寧に説明し、「なぜ今この対応が必要なのか」を理解してもらうことが大切です。
このように、J-SOX対応の実施に先立ち、内部統制報告制度の重要性を丁寧に伝えるとともに、海外子会社の担当者への配慮や工夫を積み重ねることで、現地の担当者が自発的に協力してくれる体制を築くことができます。その結果、J-SOX対応が単なる形式的な作業に終わらず、グループ全体の内部統制のレベル向上につながります。
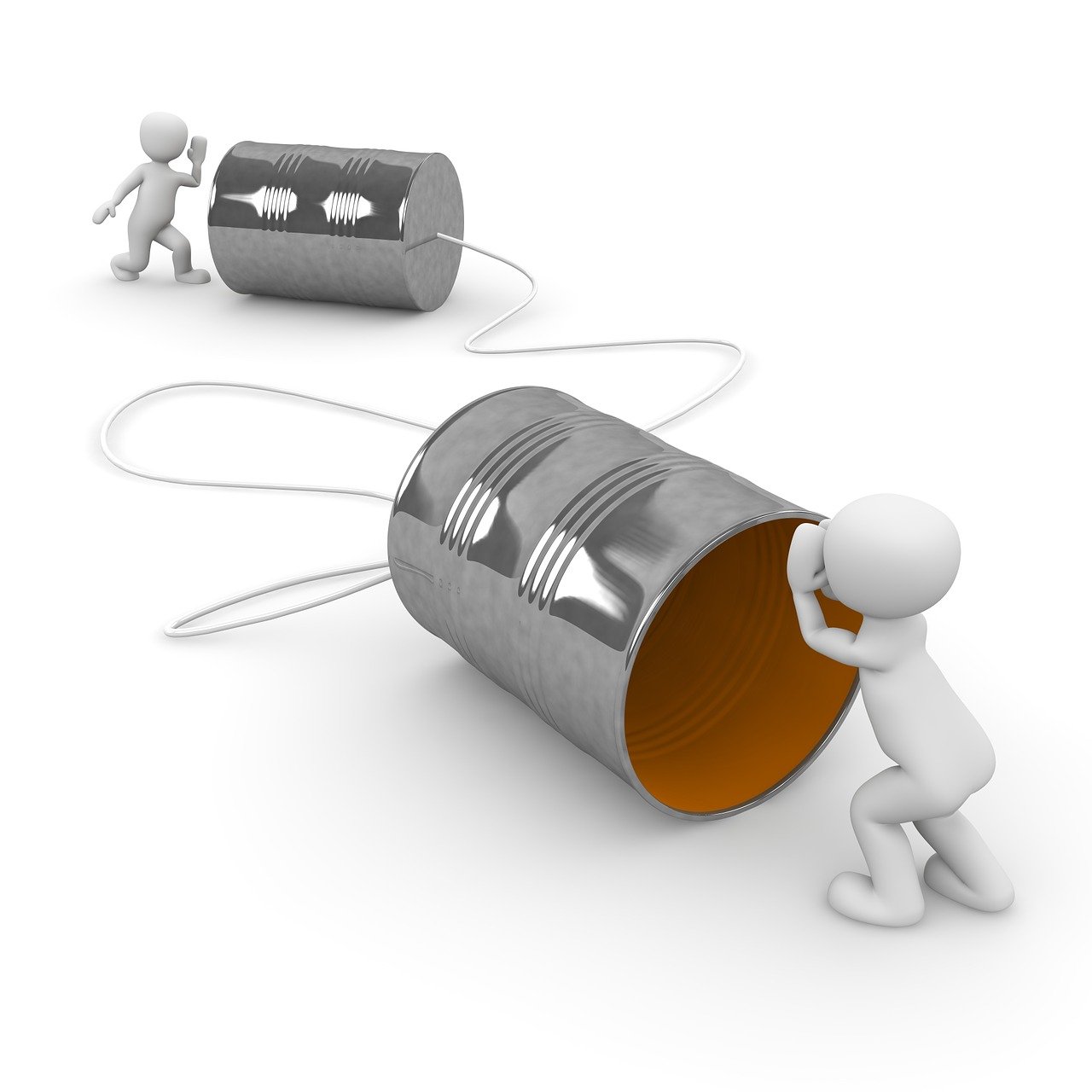
J-SOX導入における成功事例と失敗事例
海外子会社におけるJ-SOX導入の成果は、現地との関係性や制度への理解度によって大きく異なります。この目次では、円滑に評価調書・3点セットを構築できた好事例と、協力が得られず非効率な対応となった事例を紹介します。
事例1:アジア・オセアニア地域 子会社(評価調書・3点セット構築)
この子会社では、評価の初期段階でJ-SOXの概要と評価対象となる根拠を現地へ丁寧に説明しました。また、現状を把握するために、マネージャーだけでなく実務担当者も交えて、業務フローや統制状況を確認しました。統制が未整備と思われる部分についても、一方的に不備と判断せず、あるべき姿を示しながら対話を重ね、現地との合意のもとで統制の整備を進めることができました。内部統制報告制度の説明から整備・評価まで、現地の主体的な協力を得ながら円滑に進んだ好事例です。
好事例のまとめ:
・J-SOXの概要と評価対象の根拠を共有
・マネージャーだけでなく実務担当者も交えた意見交換
・統制の未整備を一方的に否定せず、対話で合意を得た
事例2:南アジア子会社
この子会社ではJ-SOXへの協力が全く得られず、J-SOX評価担当者がやむを得ず、過去の証憑やシステム名などの断片的な情報をもとに、証憑収集を行う必要がありました。その結果、通常以上の時間と労力を要する非効率な対応となりました。また、別のケースではヒアリング中に現地担当者から叱責される場面もあり、対話すら困難な状況でした。こうした背景には、J-SOXの目的である「財務報告の信頼性確保」と「日本の法令に基づく義務」が現地で認識されておらず、「日本の制度であり、自分たちには関係ない」という誤解が原因となっています。
悪い事例のまとめ:
・J-SOXの目的が現地に共有されていなかった
・「自分たちには関係ない」と他人事として認識されていた
・必要な情報提供や対話に応じてもらえず、業務が著しく非効率となった
海外子会社へのJ-SOX導入は、内部統制報告制度の目的を共有し、本社からの一方的な押し付けを避け、現地の主体的な協力を促すことが重要です。
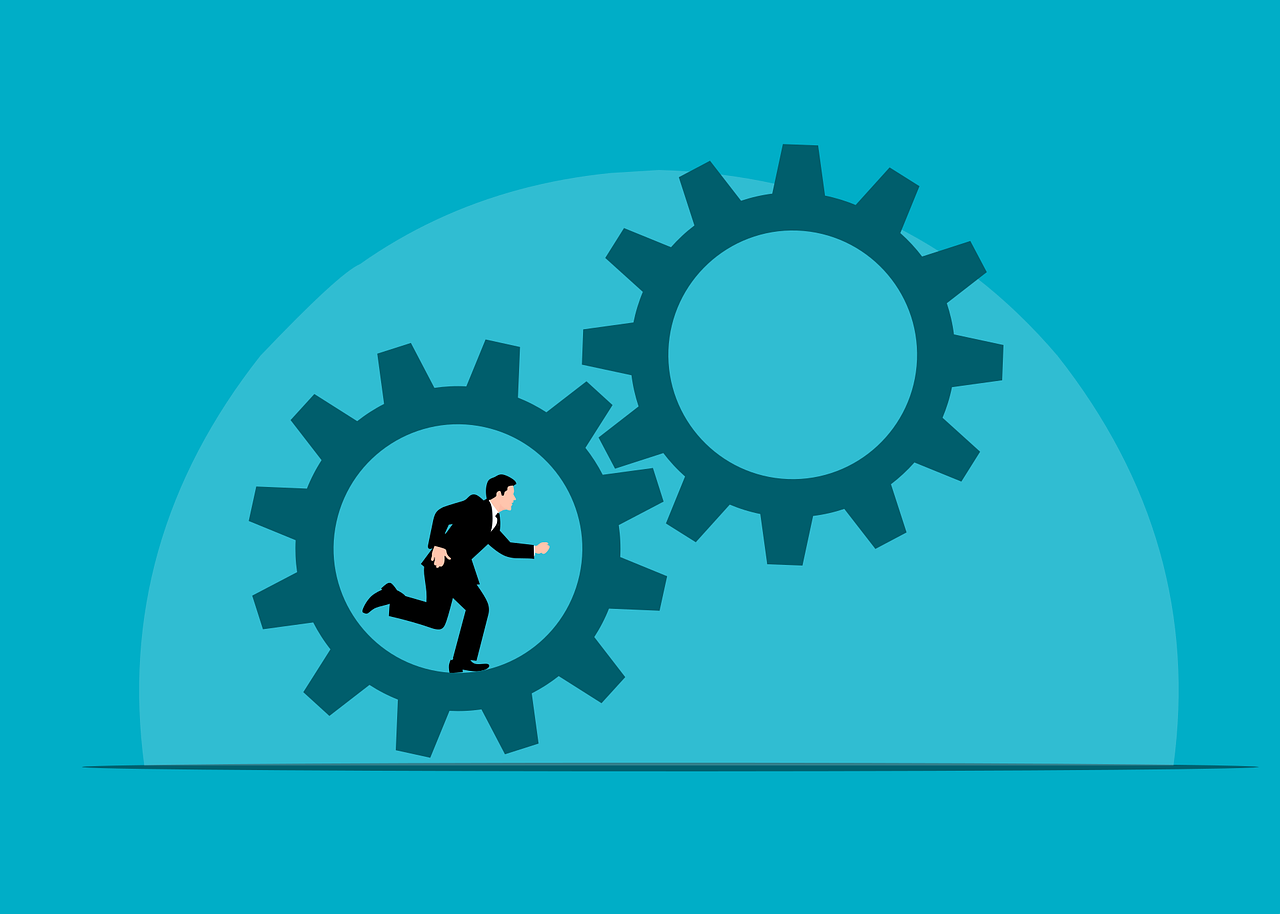
J-SOX導入後の成功事例と失敗事例
J-SOX評価が定着し、安定的に稼働している拠点では、本社・海外子会社双方の負担が軽減され、効率的な評価が可能となっています。一方で、安定した状態に見えるがゆえにマンネリ化し、変更や見落としに気づかない「落とし穴」も存在します。
事例1:安定稼働中の拠点
この拠点では、基本的に前年と同様の証憑や回答が提出され、評価結果にも大きな変化はありません。現地の担当者は、評価に必要な資料を理解しており、証憑収集もスムーズで、質問への回答も迅速に対応されます。そのため、評価担当者の負担も小さく、効率的な対応が可能です。ただし、評価の際には注意すべき点もあります。例えば、社内規程は定期的に見直しが発生するため、規程改訂の有無だけでなく、内容の変更点と周知状況を確認する必要があります。また、システムのリプレイスが行われた場合は、業務プロセスや承認経路などに影響がないかを確認することが重要です。さらに、人事異動が頻繁な海外拠点では、承認権限者の交代が行われていることがあり、評価時に最新の組織図を確認を行うことが求められます。
安定稼働中の拠点のまとめ:
・本社・現地双方の作業負担が軽減
・評価手続きの精度が高く、対応もスムーズ
・評価時は規程・システム・体制の変更点の有無に注意
事例2:安定稼働中の落とし穴(マンネリ化)
一見安定しているように見える拠点でも、更新漏れや回答の不備が蓄積しているケースがあります。セルフチェックリストを使用した今回の事例では、海外子会社が前年の回答内容を転用した結果、日付の修正漏れや質問内容の変更に気づかず、質問と一致しない回答が返されるケースがありました。対策としては、「前年と同じ=有効」とは限らないことを意識させ、質問内容と回答の整合性を確認することが重要です。また、J-SOXの目的を定期的に再共有することで、形骸化を防ぎます。さらに、メールやWeb会議だけでは見えない実態を把握するため、現地訪問も有効です。
安定稼働中の落とし穴のまとめ:
・質問の内容と回答の整合性を確認する
・J-SOXの目的を定期的に現地と再共有する
・定期的な現地訪問により、実態を確認する
安定稼働している拠点では、本社と現地の作業負担軽減等のメリットがありますが、マンネリ化により、更新漏れや回答の不備が蓄積し、J-SOX評価の有効性と信頼性を損なわれることがあります。質問内容と回答の整合性確認などを的確に行い、評価の品質を維持することが重要です。

まとめ
J-SOXは海外子会社も対象となりますが、現地では制度の目的や背景が理解されず、非協力的な対応が課題となることがあります。信頼関係の構築や言語・文化への配慮、双方向の対話を通じた制度の共有が定着のカギです。成功事例では、現地と対話を重ねることで主体的な対応が得られています。説明が不十分だったり一方的に進めると、反発や非効率を招く原因になります。
海外子会社がJ-SOXに非協力的になる原因
・J-SOXの理解不足と誤解
・文化・業務慣習の違いへの配慮不足
・人材の入れ替わりによる知識継承の困難さ
J‐SOX評価前に現場に“重要性”を伝えること
・制度の目的と意義を明確に伝える
・本社が一方的に進めることを避け、協働の姿勢を示す
・背景や目的を丁寧に説明し、自発的な協力を促す
J-SOX導入における成功事例と失敗事例
・J-SOXの概要と評価対象の根拠を共有
・マネージャーだけでなく実務担当者も交えた意見交換
・統制の未整備を一方的に否定せず、対話で合意
J-SOX導入後の成功事例と失敗事例
・本社・現地双方の作業負担が軽減
・評価手続きの精度が高く、対応もスムーズ
・継続的な見直しと対話でマンネリを防止
